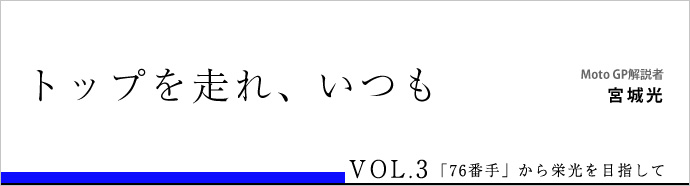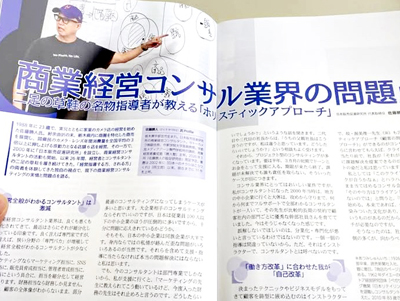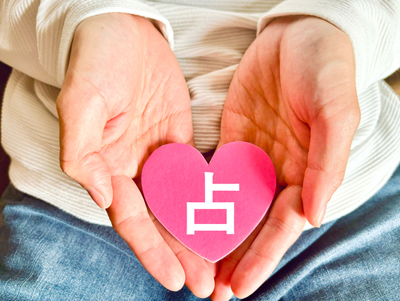トピックスTOPICS
ひとつは、できる限り「低コスト」で、それを成し遂げる必要があるということだ。
世界一のバイクメーカーであるホンダ、トップサーフアパレルメーカーのビラボン、フィットネスシューズのトップブランドであるリーボックといった、世界に名だたるブランドが私のパーソナルスポンサーとして付いてくれていたことで、私はすんでのところで「身元不明・謎の東洋人」になることを免れていたが、資金は暮らしていくだけでギリギリの状態だった。他のチームメイトのように、日中に仕事をすればこの状況も改善されるだろうが、それでは日中の仕事こそが「本業」となり、早晩「レースはホドホドに頑張ろう」といった思考に行き着くだろう。人間、誰であっても安きに流れ着かないとは言い切れない。
もうひとつは、「ライバル」があまりに身近に居たということ。ひとつ屋根の下にチームメイトも、メカニックもいる。チームメイトは、同じチームで走る仲間である以上に、最も近い場所にいるライバルでもあるし、メカニックは、何の悪意も無く、私の動向をその「ライバル」に伝えてしまう可能性がある。
彼らを出し抜かなくてはならない。その方法を考え抜いた結果、私は、「共同生活」の中から気配を消すことにした。
起床は朝4時だ。
10月のデイトナで最初の走行セッションが始まるのは朝8時。そのためには、最低でも2時間前に起床する必要があるわけだが、私の住むテキサス・キャロルトンと、デイトナのあるフロリダの間には2時間の時差がある。2ヶ月かけて、意図的な「ジェットラグ」を生み出すことにしたのだ。
「ライバル」が寝静まっている4時から、彼らが仕事に出かける9時までは、部屋の中で息を殺して腹筋・背筋・腕立て伏せ等のトレーニングを徹底して行う。息づかいすら、壁一枚隔てた向こうにいるチームメイトに悟られてはならない。文字通りの「無酸素運動」である。
家から誰もいなくなったのを慎重に確かめてから、自転車で走り出す。水も飲まず(今では考えられないことだが、バイクのレースは走行中に水分補給を行わないので当然のことだと思っていた)全力で自転車をこぎ続けるトレーニングを数セット。日中の最高気温が35℃を超える夏のテキサスは、鈴鹿8耐で最も厳しかった状況をイメージしながらのトレーニングには最適だった。あの状況でも的確に動き、脳への酸素供給を途切れさせない身体になっていれば、何も恐れるものなど無いからだ。
トレーニングコースにしていたフリーウェイの側道には、こざっぱりとした家族連れでいつでも賑わう現地のイタリアンレストラン「オリーブガーデン」が建っていた。どこにでもありそうな、いわゆる「ファミレス」の様子が今でも忘れられないのは、日本にいれば当たり前のように享受していたものすら、これから全力で掴み取らなくてはならないことを痛感させてくれたから、というのもあるが、自分の食生活があまりにもそれとかけ離れていたのも一因かもしれない。
私が2ヶ月間「摂取」し続けたのは、スーパーマーケットで仕入れてきたミートパテ──牛肉のようなものと、豚肉のようなものが混ぜ合わされた「肉のようなもの」──だ。
これを、フライパンで親の敵のように焼く。
含まれる脂が全て抜けきり、炭のようになった肉は、「食事」と呼ぶのも躊躇われるような代物であったが、「自分はいま、良質のたんぱく質を摂取している」と言い聞かせ、リンゴと牛乳の他は、ほとんどこればかりを一日2回、毎日身体の中に送り込み続けた。ひどい食生活ではあったが、「費用対効果」としてこれほど優れたものはなかったと、今でも思っている。
肉からしみ出したラードを来る日も来る日もシンクに流し続けたせいで、最後にはとうとう排水口が詰まってしまったのは、ちょっとしたアクシデントだった。これは、「ライバル」に気づかれないためにも、しかるべき方法で捨てるべきだったかもしれないが・・・幸運にしてチームの面々は私の「隠密行動」に気づくことはなく、無事にレースウィークを迎えた。
テキサスからフロリダへと旅立ったあの日以来、キャロルトンには一度も戻っていない。
最終戦「チャンピオン・カップ・シリーズ」は、通常のシリーズ戦とは少々異なる一戦だ。北米のみならず、中南米からも・・・つまり、「全米」のライダーたちがここに集って順位を争うからだ。
参加台数はフルグリッドの80台。スタートは40台ずつに分けて行われ、「ファーストウェーブ」と呼ばれる40台がスタートした10秒後に、「セカンドウェーブ」の40台がスタートする。「セカンドウェーブ」のライダーなど、走り始める前から負けることがわかりきっているようなものだが、その年の実績から導き出された私の予選順位は、80台中76番手。レースはたったの12周。
あまりに絶望的な状況、少なくとも「勝利」など望めるものではないことがおわかりいただけると思うが、初日に行われた「スーパーバイク650クラス」のレースで、75台を抜き、私はウィナーになった。
ポディウムの上では、英語の話せない私に代わって、元レーシングライダーにしてチーム監督のケビン・エリオンが上機嫌でインタビューに応え、場内を大いに沸かせた。
私の血のにじむような努力が報われた瞬間であった。
・・・しかし、久々に立つ表彰台からの美しい風景を眺めながら、これが「感動のエンディング」ではないことも、私はわかっていた。
「76番手からの勝利」はセンセーショナルではあるが、これだけでは文字通り「まぐれ」との印象が残ることは避けられない。奇跡も2度起こせて初めて意味があるものになる。それが、長いレース人生の中で学んできたことだからだ。
──2日目の「スーパースポーツ600クラス」にも勝たなくてはならない。
-
前の記事

トップを走れ、いつも vol.2 1993年8月 静寂のデイトナ トップを走れ、いつも
-
次の記事

トップを走れ、いつも vol.4 カリフォルニア生活で出会った人・コト トップを走れ、いつも