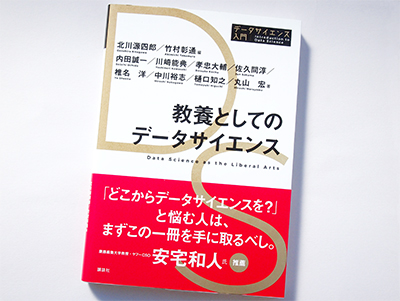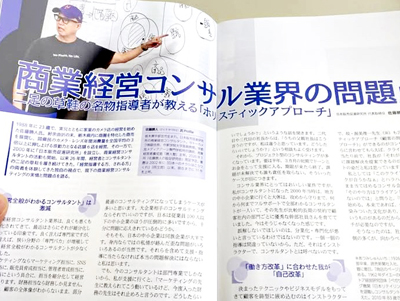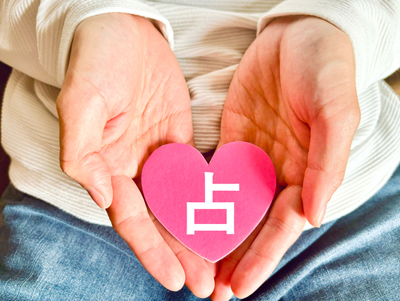土地を国庫に

法務省のサイトにはこうある。「両法律は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しを行うものです」。
このうち「発生の予防」の観点からは、不動産登記法が改正され、これまで任意だった土地建物の相続の際の登記および、それに伴い生じることの多い住所等変更――所有者が被相続人から相続人に変わるから住所が変わることも多い――の登記が義務になった。
また、同じく「発生の予防」の観点から新法を制定し、「相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設する」としている。こちらは「相続土地国庫帰属法」と略称される、土地関連のまったく新しい法律である。
デジタル課税とミニマムタックス
まず「ミニマムタックス」について言うと、これは多国籍企業を誘致するため世界各国で続いてきた法人税率引き下げ競争を終わらせ、「底辺への競争」と呼ばれた不毛なチキンレースに国際協調のもとで終止符を打つものだ。今回の合意で「最低でも実効税率15%」とミニマム(下限)が決められたことにより、これを下回っている国は今後は明確にタックスヘイブン(避税地)と見なされ、それらの国に子会社を設立している企業は課税が強化されることになる。
次いで「デジタル課税」とは、これまでは工場や店舗などの恒久的施設(PE:Permanent Establishment)が国内にないとその国は企業に課税できない原則だったのが、PEがなくても自国内で商材の売上が生じていれば企業に対し課税できることにするものである。典型的にはGAFAに代表される、ネット経由のサービスで売り上げを得ている国際寡占企業が対象になる*1。
課税原則が変更されるのは約100年ぶりで、OECDの試算では年間約1250億ドル(約14兆円)の利益に対する課税権を、徴税できてしかるべきなのにできなかった国に対し、配分できるという。日経新聞はコールマン事務総長の、「国際的な課税ルールはより公正で機能的なものになる。多国間主義にとっての大きな勝利だ」という言葉を伝えている*2。
ナショナリズムとNationalism
さらに言えば、デジタル課税への合意をアナロジーで理解するならば、「プロダクトからマーケットへの主軸の変更」を読み取ることもできるはずだ。製品なりコンテンツなりがどの国で生産されているかではなく、市場がどの国にあるかで課税対象=事業利益の所在を決める話だからだ。
そして市場が自国にある場合、それらの国々――多国籍企業の市場国は複数だから複数形だ――は当該事業の全世界収益に関し、利益が10%を超えて出たぶんを超過利益とし、自国内での売上高に応じて当該企業の事業所得としてそれぞれ引き当て、課税することができる*3。企業は超過利益とされたくなければ世界トータルでの利益率を10%以内に抑えなければいけないわけで、今回の合意は企業の利益率に一種の総量規制をかけるものとも言えるだろう。
そう捉えると、ことは「多国間主義としての自国主義」というInter-Nationalismの文脈に留まらず、民間の私企業の事業活動に対し、各国が「国家」をその上位においてその内容――原価圧縮の工夫や売価の設定――にまで関与してきたのだと見ることもできる。それほどまでに一部の産業資本の力が巨大になり過ぎたのであり、また、国家とは本来どんな機能を果たすものであったかについて、世界の各国が一斉に目覚めたということでもあるのだろう。
多分に直観を含む私見だが、そう思えてならないのである。
土地、国土、国家
日本では、明治政府による地券制度の導入以降、土地の所有権の成立に関し、私人の権利・義務と国家の権限・責務の関係が法的にあいまいなまま推移してきた*4。その結果、国土交通省の2016年の地籍調査で所有者の所在不明土地が国土の5分の一にのぼり、法務省が2017年に全国10地区を対象に行った調査では、50年以上にわたって登記の変更がなく、相続登記の未了が疑われる土地が大都市で6.6%、中小都市・中山間地域では26.6%もある*5。ドイツや韓国、台湾のように所有権の登記が所有権の移転(相続や売買)成立のための要件になっておらず、登記をしなくても相続や売買ができることが、このていたらくにつながっている。
この際、あえて“ていたらく”と呼ぼう。イギリスでは全国土は国王に属するという理論上の前提がある。土地所有権は利用権に近く、期間が過ぎれば土地は国王のもとに返る*6。台湾では憲法第143条で土地は国民全体に属するとされ、「人民が法により取得した土地の所有権は、法律の保障と制限を受けなければならない」と明文化されている*7。
翻って本邦だ。かつて郷村の糧を支えた農林地は戦後の高度成長期に「土地神話」に入れられ利殖材料となり、土地が土地であるままでは、即ち、いかに自然の再生産能力が豊かでも売買において価値を見出されなければ、所有者からも、基礎自治体からも、国家からさえも“お荷物”とされるところまで成り下がった。注4で参照した座談会に出席した法務官僚二人の発言からも、公務員として法的な建付け論に終始せざるを得ないとはいえ、最後は国土は国家が護持すべきだという意思は、伝わってこない。
「国民の負担、税金の負担で土地を管理しなければならなくなる国の立場として、管理・処分に大きな負担があるものでは引き受けられないが、所有者不明土地の発生予防の観点から、そのような負担がないものであれば何とか引き受けられるというところがあった」とは、相続土地国庫帰属法の立案を担当した法務官僚の言である。――わかる、わかるけれども、国民はそんな話を聞きたいのではないはずだ。
その意味で、デジタル課税のように物理的実体を伴わない無形資産でさえ国家から目が注がれるようになったのと同じタイミングで、究極の物理的実体を持つ有形資産である「土地」に国家が関与する端緒がついに本邦でも開かれたことは画期的だ。“お荷物”を処分しやすくなるというような捉え方ではなく、国際経済の分野で芽生えた「健全な自国主義」にならって、議論が深まるよう期待したい。
*2 「デジタル課税、利益14兆円分に「網」 世界で分配へ」(日本経済新聞 2021/10/10)
*3 「デジタル課税・ミニマムタックスの大枠合意」(大和総研レポート 2021/7/21)PDF図表1参照
*4 有斐閣刊『ジュリスト』2021年9月号特集「所有者不明土地と民法・不動産登記法改正」座談会より
*5 『人口減少時代の土地問題』(吉原祥子著・中公新書・2017年)p11
*6 同上p125、126
*7 同上p132
(2021.11.10)