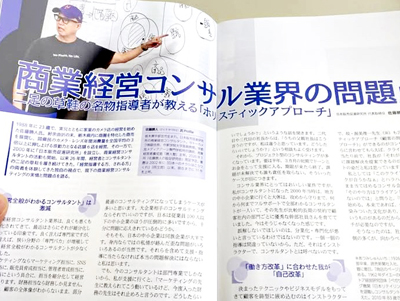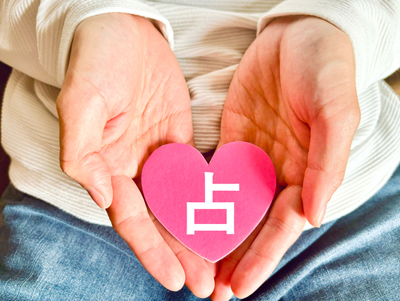障害者差別解消法は雇用を促進するか

日本には「障がい者」とされる人が約787.9万人暮らしている(2011年統計)。人口比で言えば6.2%、15人に1人は身体や心になにがしかの障害を持っているというのが我が国の現状だ。このうち就労可能と考えられる人、すなわち一般的に現役世代と考えられる年齢層(18~64歳)で入院していない障がい者は、身体障がい者111.1万人、知的障がい者40.8万人、精神障がい者172.4万人(20~64歳)。2014年の統計を見ると、雇用障がい者は49.5万人で、働いているのは就労可能性がある障がい者のうち15%程度に過ぎない。一般的な就労率が75%程度なのにくらべ極端に低くなっている。
そんな現状を改革すべく、政府は近年、障がい者雇用に関する法整備を矢継ぎ早で実施してきた。2013年には障がい者の法定雇用率が引き上げられたのに続き、今度の改正では機会均等を明確にうたい、配置や昇進、賃金の支給などについて平等化が義務づけられる。
多くの企業が人手不足に足を引っ張られている
障がい者雇用を考える時、近年もっとも注目すべきは深刻化する人手不足だ。2016年1月の有効求人倍率は1.28倍という高さだが、都市部の事態はさらに深刻であり、東京都では1.88倍にものぼる。
人手不足は企業に対し機会逸失によるダメージをもたらす。アベノミクスで一定の好況感が出ている中、受注のチャンスを逃すことは大きな損失と言える。日本商工会議所が2015年8月に発表したアンケート調査では、約半数の企業が「従業員が不足している」と回答した。
企業活動への影響も顕在化し始めており、大手デパートでは従業員が確保できないことから営業時間を短縮する動きが出始めている。高島屋では大宮店と大阪堺店において一部フロアの営業を30分短縮、日本橋店の営業を1時間短縮した。三越伊勢丹ホールディングスも三越日本橋店、伊勢丹立川店・浦和店の閉店時刻を30分繰り上げた。インバウンド景気にわくデパートにとって営業時間の短縮は歯がゆい限りだが、人手が足りないという事実の前にはいかんともしがたい。昨今は多くの企業がこの人手不足による損失を回避するため、人材確保に奔走している。
働きたい障がい者は起業するしかない?
いっぽう、障害者の側には社会参加の一環として働く場を求める気持ちが強い。これまで障がい者にとっての労働は「チャリティを受けること」とほぼ同義だった。努力しても報われず、賃金は総じて低い。厚生労働省の資料によると、常用労働者全体の平均年収は262万円(2014年)だが、障がい者では身体障がい者223万円(2013年)、知的障がい者108万円(2013年)、精神障がい者159万円(2013年)となっている。福祉的な色合いが強い就労継続支援の賃金はさらに低く、A型で69万円、B型では14万円にとどまる。
「働いて得た収入で自活する」というごく当たり前の暮らしをしたければ、起業するしかないのが現実だ。もちろん簡単なことではないが、株式会社仙拓のような好例も現れ始めている。同社は脊髄性筋萎縮症という難病を抱える19歳の青年が設立した企業で、ホームページ制作や印刷物のデザインを請け負う。「僕には働く場所がなかった・・・だから会社をつくろうと思った」――代表取締役である佐藤仙務氏は起業動機についてそう語る。まだまだ数は少ないものの、同社のような成功例が出てきているのは、障がいを持つ人たちに「働きたい」という真摯なニーズがあるからこそだ。
カギとなるのは国際基準に基づく理解と工夫
人手不足に悩む企業と働きたい障がい者――双方のニーズが合致する障がい者雇用には大きなビジネスチャンスが潜んでいる。ビジネスの現場では「障がい者=お荷物」という認識が一般化しているが、高いビジネススキルを持つ人が疾病や事故などにより障がい者となったため働く場を失ってしまうケースも少なくない。
大きな可能性が眠る人材の鉱脈を活用するカギは「生活機能分類」という考え方にある。例えば日本では下肢麻痺という障がいについて「麻痺があるから仕事ができない」と考えがちだ。海外ではこれは古い認識とされ、より新しい「国際生活機能分類(ICF)」に基づいて、「仕事に不自由があるのは麻痺だけでなく『職場や交通機関がバリアフリー化されていない』『介助する人がいない』などの問題が複合的に作用した結果」と考える。この視点に立って状況を見直してみると、環境を整え介助者をうまく確保することで、健常者と同じように能力を活用できる障がい者の存在が見えてくる。
ハード・ソフト両面でバリアフリー化が進んだ職場は、障がい者だけでなく高齢者や妊婦などの弱者にとっても居心地のよい職場であり、有能な人材が集まりやすい。短時間労働や在宅勤務など、障がい者にとって働きやすい制度の導入が職場の効率化につながることもある。肉体的弱者を大切に考えることから業務の無駄や非効率な制度が見えてくれば、企業はよりシェイプアップされる。日本の文化は古来、異世界から来訪して新たな文化をもたらす「まれ人」を刺激として育まれてきた。企業においてもそんなマリアージュがもたらすメリットは大きい。
マクロ的な視点で見るなら、雇用された障がい者が新たな消費者となり、経済の活性化に資するという利点もある。公的な負担が減少するため、ビジネスに関わる税負担の軽減につながり、日本社会全体の活力アップにもつながる。
人材不足の解消策として女性や高齢者、外国人に目をつけた取り組みはすでに進められているが、障がい者に着目する事業者はまだ少ない。有能な人材が眠る新たな鉱脈は企業にとって発展の起爆剤ともなり得る。チャリティではなく、あくまでビジネスの目線で障がい者雇用を検討してみる意味は大きい。
(ライター 谷垣吉彦)