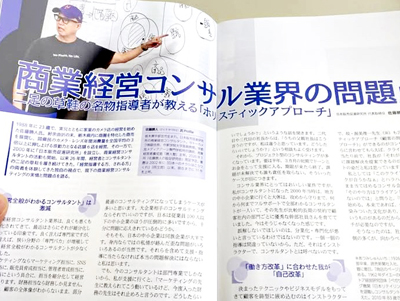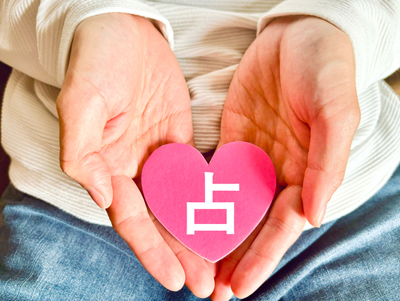伊達男が語りつくす
仕事も人生もデキる人のスタイル
ジローラモ氏から飛び出してくる 「ハッピー」 という言葉。まるで無邪気な子供のように楽しそうにインタビューに答えるその姿に、聞いているこちらまで楽しげな気分になってくる。ジローラモ氏は 「ぼくはいつまでも子供でいたいんだ」 と付け加えた。実際の彼の少年時代はといえば・・・。
イタリアにいた普通の少年

ぼくはイタリアのどこにでもいるような普通の少年でしたよ。ちょっぴり恥ずかしがり屋だったけど、いい子でしたね(笑)。 マンションに暮らしていたので、共用スペースとなる大きな庭があってね。学校から帰ったらまず宿題を終わらせてから、そこに仲間が集まる。皆でサッカーをやったり、遊んだりしていましたから、日本の子供たちとそんなに変わらないんじゃないかな。
イタリアはサッカーが盛んな国ですから、だんだんストリートからクラブチームのジュニアユースなんかに皆で進むようになって、ぼくもナポリというチームのジュニアユースに進みました。だけど、当時のぼくはプロのサッカー選手になるつもりはなくて、あくまで遊びの延長。当時、一番興味があったのは女の子のキモチかな。男の子と女の子って、心理的に大きな違いがあるじゃないですか。だから、「なんで違うんだろう?」 とか、「なんで女の子にモテる男の子と、そうではない男の子がいるんだろう。その違いはなんだろう?」 とか、そういう人間心理にすごく興味があった。ぼくが子供の頃に周囲でモテていたのは、皆かわいらしい美少年ばかりだった。ぼくは美少年ではなかったので、もしかしたらその悔しさもあったのかな(笑)。 「美少年たちに勝つにはどうしたらいいか」 なんて、そんなことばっかり考えていました。
そんなジローラモ氏の人生に大きな転機が訪れたのは大学時代だった。彼の父親はイタリアで建築会社を営んでおり、大学でも勉強をしながら建築家になるための経験を積まされたのだという。
父親が経験させてくれたこと

夏休みともなると、父親が経営している建設会社の現場に行かされるんですよ。とはいっても、そこで現場作業をするわけじゃないんです。父親の名代として、現場の監督役として派遣されるんですね。監督役ですから、ずっと年齢が上の作業員や、現場経験の長い作業員たちを管理しなくちゃいけない。でも、そこでちょっとした戦いがあるんです。向こうは労働時間をごまかそうとしたり、何かとズルしたがるんですよ。7時間しか働いてないのに、「いや、8時間働いたぞ」 とかね(笑)。 だから現場では彼ら以上にズル賢くなるというか、機転を利かせられなければ、監督役なんか務まらなかったんです。父親の考えとして、大学在学中にそうした現場を踏ませることによって、就職して1年目から即戦力になれるという目論見があったわけ。イタリアでは、就職して最初の1年は研究生扱いになることが多いですから、現場経験があるほうが、より早くお金を稼げる。今から思うと、ある種の英才教育を受けさせてもらっていたのでしょう。
でも、ぼくはその時も仕事漬けになるのが嫌だった。仕事が嫌なのではなくて、仕事しかできないオヤジになりたくなかった。だから仕事をしながら友達とも遊んだし、女の子ともデートをしたし、旅行にもたくさん行きました。自分の心を自分で決めつけることをせず、いつもやりたいことやその時の気持ちに対してオープンでありたかったんですよね。
たとえばね、こんなことがありました。私が大学生の頃、イタリアでも大きな地震を経験したことがあるんです。いろいろなところで家や建物が壊れて、国を挙げて復旧作業をすることになった。そこで、「この建設会社はこの村の修復を担当しなさい」 というふうに政府から指示があるんです。ぼくも2000人くらいが暮らす村の担当になって。そのときの思い出がすごく印象に残ってるんですが、その村の人たちと、もう本当に仲良くなれたんです。地震で皆気持ちは沈んでいたはずなのに、ぼくがオープンに接したら村の人たちもオープンに接してきてくれた。大変な状況の中なのに、いろんなハッピーを見つけることができた。そのときに思いました、「自分からハッピーを伝えていくことができると素敵だな」 って。
ジローラモ氏が初めて日本の土を踏んだのは、その後のこと。父親の友人が、日本人建築家をテーマにした書籍を書くことになり、取材に同行したのだ。「探検家になったみたいに毎日ワクワクが続いた」 と語るように、初めての国、触れたことのない文化、出合ったことがない食習慣などに胸を躍らせ続けたジローラモ氏は、やがて日本で生活することを決意する。そして日本の飲食業界に新しいカルチャーをもたらした。
蕎麦カルチャーを変えた名店
以前赤坂で 『SOBA GIRO』 という蕎麦店を手掛けました。「イタリア人が蕎麦屋をやる?」 と最初はいぶかしげに見られましたが、ぼくは自信がありました。実は、日本とイタリアは “麺文化” という共通点があるんです。同時に、日本もイタリアも、「食材の良さを生かす」 という食への価値観が同じ。たとえば、パスタの上にタラコやいろんなものを乗せますが、食材の気持ちをわかることができると、何でも応用が効くんです。「蓮根っておもしろい食材だな」 とか、「大根は何にでも応用が利くぞ」 とか。沖縄のゴーヤだってすごくおもしろい食材でしょ? それが蕎麦に変わっただけで、大それたことをしているわけじゃなかったんですよ。