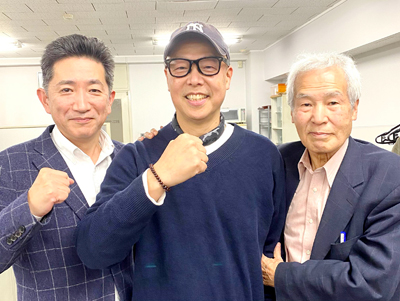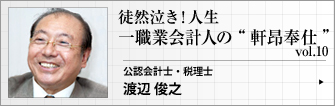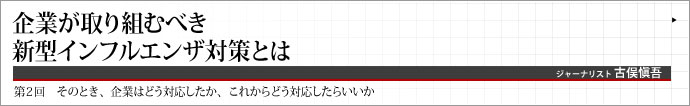日本にPublicはない

パブリックリレーションズ(Public Relations)とは、組織とその組織を取り巻く人間(個人・集団)との望ましい関係を創り出すための考え方および行動のあり方である。19世紀末から20世紀にかけてアメリカで発展し、日本には第二次世界大戦後の1946年以降にアメリカから導入された。‥略‥アメリカで教科書として定評がある『体系パブリック・リレーションズ』では、次のように定義されている。
「パブリックリレーションズとは、組織体とその存続を左右するパブリックとの間に、相互に利益をもたらす関係性を構築し、維持するマネジメント機能である。」
教科書では単独語で「パブリック」とある点に注意すべきだ。本来Public Relationsは「Public」と「Relations」それぞれの含意を踏まえて初めて成立するのであり、日本語が取り入れる際も本来であれば、パブリックとリレーションズをいったんそれぞれ概念化しなければならない*3。
しかるに社会学者の宮台真司氏によれば、日本には「Public」に相当するものはない。他者性の概念が未熟で幼稚だからだ。代替しうるものとして「世間」があったが、その構成基盤である本当の意味での仲間関係が現代では得づらくなっており、各人が“見たいものだけを、見たいようにだけ見る”社会が続いているという*4。
コンテンツマーケティングとブランドジャーナリズム
ブランド(=企業)自らが取材をし、編集した記事やストーリーを自らのWebサイトやソーシャルメディアなどを通じて、直接生活者に発信していくことで、ブランドがジャーナリスティックな視点と手法で情報を拡散することを意味する。
東洋経済の特集は、近年、上記解説に見られる各工程――取材、編集、発信、拡散――にニーズを見出したパブリックリレーションズ専業会社(以下PR会社)の参入が激しさを増しており、既存マスメディアの衰退もあいまって社会全体が“PR漬け”になっている、と報じたものだった*5。
筆者もフリーライターという仕事柄、業界で言うブランディング出版の書籍には日常的に携わっている。その実感に即して言えば、企業(経営者)が自社の事業やサービスについて語る際に業界や同業他社や消費者について意見なり論評なりをすることは当たり前で、何も今さら“ジャーナリスティック”と形容する必要はない。
それでも形容するからにはそれなりの必然があるわけで、社会構想大学院大学特任教授の高広伯彦氏の「ジャーナリズムは職能やスキル、技法である」とする立場とともに、「コンテンツマーケティングを説明するときに、多くのマーケターが近しい概念としてブランドジャーナリズムをあげてきた」という、最早古くなった普及の経緯の説明が最もすんなり腑に落ちる。
最早古くなった、としたのは「ブランドジャーナリズム」でGoogle検索をかけたとき結果の2ページ目に出てきた7年前の記事でこの経緯を見つけたからで*6、今年4月に民放キー局の人気キャスターがトヨタの自社メディア『トヨタイムズ』の“所属ジャーナリスト”に転職したことをめぐる侃々諤々の議論や、今年1月に「ブランドジャーナリズム」をそのまま社名にした企業が創業したことに関する記事が埋め尽くす1ページ目と比べると、隔世の感があるからである。なるほどネット検索は1ページ目だけで止めていてはいけないと再認識させられた次第だ。
テレビ報道の終わりと卒牛式CM
前者の事態を意味論的に理解するには、例えば名古屋4局が合同で運営する動画配信サービスLocipo(ロキポ)のCMを4局の女子アナの共演で制作・放送しているのと比べてみればいい*7。自局のサービスを自局の社員を使って訴求するぶんには何も問題はない。問題は、最早どのテレビ局だったか思い出せないが、自局の報道枠のアナウンサー――確かそうだった――に通常のCM枠で一般の商品を宣伝させたことだ。彼女のタレント性の部分だけ切り出して“商品”としてCM出稿企業に売り込んだのが局だったのか、本人だったのかはわからないが、意味論的にはこれは局の身売りである。筆者はあれで「テレビは終わった」と思った。
卒牛式CMに関しては、公式動画はもうネットから削除されているが、個人ユーザーがSNSにあげたものを視聴できる。本稿の執筆にあたり筆者は個人ブロガーの分析も参照し*8、当該CMが自分の感覚に照らして一線を越えていたこと、あれで広告を名乗ることに当時腹を立てたことを再確認した。――と同時に、今後も同種のPRは現れるだろうことも。
なぜならこの種の原始的コンテンツは強いからだ。ブランドジャーナリズムをジャーナリズムと分けたいならば、広告をジャーナリズムと分けたいならば、あるいはPublicなき世界でパブリック・リレーションズを行おうとする際は特に、この種の“強い”コンテンツとどう距離をおくかが分水嶺になるだろう。しかもその距離は疎隔という意味のそれではなく、むしろ溶け合うニュアンスも含めた“間(あわい)”という言葉で表されるそれであり、そうであって初めて、それを介して分けられた両者が豊かに育つ。
ちなみに、ユーモアはドイツ文学畑でフモール(Humor)と言ったときには“距離をおきつつ(=感情的に入れ込むことなく)包摂する”というニュアンスを持ちます。読者諸兄におかれましては、本稿もユーモアを持ってご参読くださいますよう・・・。
*2 パブリックリレーションズとは(公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会)
*3 だから本稿も地の文の箇所では中黒を入れて表記する。
*4 【東京ホンマもん教室】戦後76年“あの戦争”とは何だったのか〜ホンマもんの保守をめぐって〜 ゲスト:宮台真司(対談テーマ:日本の劣化と大衆社会)(TOKYO MX)17:20~ 他
*5 「PR漬け社会」の到来で起きた情報流通の主役交代 6兆円の広告市場に染み出す、新興勢力の正体(2022/11/14)
*6 コンテンツマーケティングの普及により、再び注目を集め始めている「ブランドジャーナリズム」とは?(Content Marketing Lab 2015.04.27)
*7 Locipo(ロキポ)、新CMで名古屋4局の女性アナウンサーが共演(Screens 2021/3/5)
*8 炎上したブレンディのCMを冷静に分析する(MistiRoom 2015-10-03)
(2022.12.7)