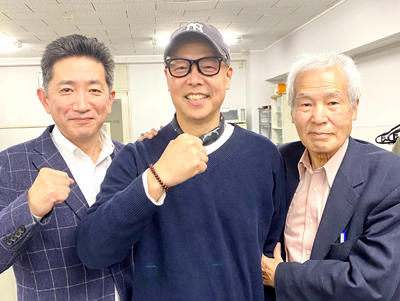写真を学ぶために大学は日本大学芸術学部写真学科を選んだ宮澤さん。しかし、入学当初はほとんどカメラに触れたこともないくらいの素人。志を持って入学してきた同級生たちとの間にギャップを感じていたという。
赤外線写真に衝撃を受ける
入学はしたものの、これまで何も経験がないし、自分が何を撮りたいのか、何を撮ればいいのかさっぱりわからない。周りの人たちはアマチュアのフォトコンテストの常連みたいな方ばかりだったから、目的もなく入学してきたように見える僕を見て、批判めいたことをいう方もいましたね。僕の甘さに腹を立てていたのかもしれない。
そんなふうに最初の1年は何もわからないまま、同級生が紹介してくれたカメラマンのアシスタントなんかをして、後は遊んで過ごしていました(笑)。でも、2年生になる少し前に、ある先生が僕の行く末を心配してくれて、フォトジャーナリストとして活躍した三木淳先生の授業に参加するように勧めてきましてね。アドバイスに従って2年生から三木先生の授業を聴講しました。三木先生は、「まずお前は何が撮りたいのか見つけろ。そのためにたくさん写真を見ろ、とにかく見ろ」と言うんです。それで大学の図書館に通ってあらゆる写真集を見まくりました。
その日々の中で見つけたのが、赤外線撮影をした作品です。幻想的で非現実的な風景が写されていて、衝撃を受けました。そして、こういう作品なら自分も撮れるかもしれない、撮ってみたいと思ったんです。のめりこむと集中するタイプなので、それからは赤外写真を撮ることに没頭しました。出来上がった作品を三木先生に見せたら、絶賛してくれたんですよ。あれは嬉しかったですね。卒業制作では日本大学芸術学会奨励賞を受賞できたのもいい思い出です。
自分を導いてくれる師との出会いを経て、撮影すべきテーマを見出すと、その才能をいかんなく発揮し始めた宮澤さん。大学卒業後は赤外線フィルム使用した処女作『夢十夜』でNY ICPインフィニティアワードの新人賞を受賞する。その後は作家性の強い作品だけでなくファッション・広告の分野に活動の領域を広げた。
被写体の心に寄り添う撮影を
海外ではそうでもないですけど、日本だとアートだけで食べている写真家ってほぼ皆無に等しいんです。それで、撮りたい作品を撮り続けるいっぽうで、商業的な分野の仕事も始めました。ちょうどその頃、ファッションデザイナーの三宅一生さんや山本寛斎さんと知り合う機会がありまして。そうした出会いを通じて、ファッションや雑誌の仕事をたくさん手がけるようになったんです。当時は商業的な仕事でも、ある程度は自分の感性を活かして好きなように撮影ができたし、いい時代でしたね。
 商業誌を撮りつづける中で、グラビアの仕事も増えていきました。当時の僕はコミュニケーション能力がさほど高くはなく、被写体の本質を引き出すグラビアの仕事ができるかどうか、不安ばかりでした。でも、篠山紀信さんや荒木経惟さんら日本で有名な写真家って皆さん女性を主に撮っているんですよね。そう考えたら、自分も写真集やグラビアで有名になれば写真家としての作品も注目してもらえるかもしれないと思いました。そういう打算的な気持ちもあって、グラビアにも挑戦したんです(笑)。
商業誌を撮りつづける中で、グラビアの仕事も増えていきました。当時の僕はコミュニケーション能力がさほど高くはなく、被写体の本質を引き出すグラビアの仕事ができるかどうか、不安ばかりでした。でも、篠山紀信さんや荒木経惟さんら日本で有名な写真家って皆さん女性を主に撮っているんですよね。そう考えたら、自分も写真集やグラビアで有名になれば写真家としての作品も注目してもらえるかもしれないと思いました。そういう打算的な気持ちもあって、グラビアにも挑戦したんです(笑)。おかげで苦手だったコミュニケーション能力もある程度は克服できましたね。グラビア撮影は被写体の容姿だけでなく、感情などの内面的な部分も見せなくてならない。でも、相手は人間ですから、乗り気がしない時もあって、短い時間でその魅力を引き出すのが難しい。試行錯誤する中で、結果として僕自身が確立した撮影手法は、無理をしないということです。
相手が喋らない時は、自分も喋らない。もともと喋りが得意ではなくて、暗い気持ちでいる人の気分を盛り上げられるような芸達者でもない(笑)。だから、相手の気分に寄り添って、元気がないようなら笑顔を要求するのではなく、「今の気分のままで撮っちゃおうか」と撮影してみる。
あとは、喋ることもなるべくその人物の内面に迫る言葉を投げかけるように意識していました。例えば、撮影に来る前に何を食べたかとか表面的なことではなく、なぜ女優になろうと思ったのかとか、仕事で楽しいことは何なのかなどと、その人の本質を垣間見れるようなことを聞く。
若い人だとけっこう、何も考えずに流されているだけの人もいるんですよ。「どうして自分はこういう仕事をしているんだろう」ってね。そういうモヤモヤしている本人の気持ちを少しずつ変えていけるような会話を心がけていました。